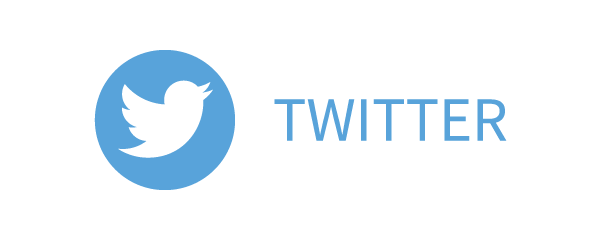2018年4月19日、城北信用金庫と広報PR支援を手掛ける株式会社バリュープレスの共催トークイベント『NACORD TALK (ナコードトーク)』がRYOZAN PARK巣鴨で初開催されました。

本イベントは、2018年1月に地域の中小企業向けPR支援の業務提携を結んだ二社が、事業者同士の出会いと学びの場として企画したもの。
今回はそのキックオフイベントとして、メイドインジャパンの工場直結ファッションブランド『Factelier(ファクトリエ)』代表の山田敏夫氏、シェアハウス&オフィス『RYOZAN PARK(リョウザンパーク)』代表の竹沢徳剛氏をゲストに迎え、城北信用金庫理事長の大前孝太郎氏とともにトークセッション。バリュープレス代表の土屋明子氏による進行のもと、2時間にわたって繰り広げられたトーク内容を大公開します!

満場御礼でスタート。テーマは「私たちの経済圏を作ろう」
NACORD TALKが掲げるテーマは「私たちの経済圏を作ろう」。
私たちの経済圏とは、
1.サービスや商品の前に、自分たちの思い描く世界がある(信念・価値定義)。
2.それに共感する社員やパートナーがいて、一緒に創り上げるチームがある。
3.完成した商品や価値に対して、共感するお客さまがいて、売上につながる。
そういったサイクルが回っている状態を「私たちの経済圏」と定義。
大衆マスに売れるものを作る、売上を上げるという基準ではなく、企業独自のモノ・コトを作り上げることをテーマとし、ゲスト3名それぞれが目指す「私たちの経済圏」について、想いや経験談を語りました。

最初の共感者は社員?ユーザー?
土屋氏:
ではまず、最初のテーマですが、ご自身が叶えたい世界観の、最初の共感者となる人。おそらく社員やスタッフになると思うのですが、その人たちはどのようにしてご一緒することになったのでしょうか。新たな採用、既存の社員への説明など、それぞれの会社のステージによってお三方異なると思うのですがいかがでしょうか。
山田氏:
僕は起業してから2年半、1人でやってきて、その間は6~7人のボランティアに支えられていました。何が重要かというと、熱狂的なファンを作るには、最高な商品や仲間だけじゃダメで、まず最初に使命感が大事だと思うんですよね。
僕の場合は、日本のものづくりを復活させる。そして日本ブランドを世界へ。その使命にこの指止まれで集まった人でした。最初の社員はその中のスタッフの1人で、もうそれは初恋の告白みたいに緊張して話をしたのをよく覚えています。
土屋氏:
城北信用金庫の場合は、既に組織がある中での変革だったと思いますが、どのようにして意識を変えていかれたのでしょうか?
大前氏:
伝統的な金融機関の中で、「いや、金融じゃないんだよ」と言うのはやはり大変でしたね。自分達のお金ではなく、預金者のお金を安全な範囲を見定めて運用するというのが金融機関の使命。もともと僕たちは、お金を貸出しする方ではなくて、預金を安定的に運用することで、お金と同等の決済手段を社会に提供する組織なわけです。で、公共性が高いので免許制にすると。そういった諸々を考えると金融で差別化していくビジネスは難しいと考えています。

だからこそ、それ以外のところで解決できるソリューションがないか。地域の賑わいや子供達の環境作りなど、金融以外のサービスを提供することは、法令違反じゃないんだからやろうよと。そう言い続けていましたが、なかなか理解浸透には至らなかった。
そんなときに今のような低金利の時代を迎え、金融機関が利益をあげにくくなってきた状況が、逆に分かりやすい環境になってきたわけですね。気がつくと「あなたが言っているのも一理あるかな」という感じになって共感してくれる人が増えてきた。というのが実態かなと思いますね。そういう意味ではマイナス金利もいいかなって、ちょっと強がってますけどね(笑)。
竹沢氏:
最初、僕は1人で始めたので、住人たちに仲間になってもらわないといけない状況でした。最初に集まる人たちがカルチャーを作ると思っていたので、高校の先輩や東日本大震災の復興支援活動をやっていた時の仲間や、その時の同じビルにいた建築事務所の所長など、肝胆相照らす人に「住もうよ!」と(笑)。
で、住んでもらって一緒にカルチャーを作って行こうと思っていました。逆にうちのカルチャーには合わない、と思った人にはいくらお金を積まれても断っていました。部屋は空いてるのに武士は食わねど高楊枝的を装い、当時は苦しかった時期もありましたが、それを乗り越えたらすごくいいカルチャーのシェアハウスになりました。それはシェアオフィスも一緒で。一緒に作っていこうよとか、オープンでポジティブな考え方ができる人が集まってきはじめましたね。

あとは自分の弱さをさらけ出すこと。僕はよく自分のことは穴だらけの大風呂敷だって話をするんだけれども。「ノリさん(竹沢氏)、しょうがないな、助けてやろうか」と人が集まってきた感じですね。そこは本当にありがたいなと思います。
自分の原体験だけは絶対に揺るがない。最高に欲しいかどうか。
土屋:
みなさん想いがあって始められたわけですが、そのご自身の描く世界観や想いを伝えるためのメッセージというのは、最初から確固としてお持ちだったのでしょうか。どのような変遷があったのかお伺いできますか。

竹沢氏:
自分が成長するにつれて作りたい欲求も変わっていきます。例えば、シェアハウス作ったときは独身だったので、みんなでワイワイすればいいよなって思ってたんですが、自分に子供ができると、今2歳の子供に対して最高の環境を与えたくなるというふうに、だんだんと変わってきています。
でも、地域で子供を育てるとか、みんなで働く、子育てする、遊ぶっていう生態系を作ること、コアの想いは変わらない。こちらが発信するメッセージというよりも、コミュニティに来る人たちの世代や背景が変わってくるので、そういう人たちの欲しいものをいかに取り入れて行こうかと考えながら、さらに、そんなに欲しいならやろうよって旗まで立てさせちゃいますね。一緒にやろうぜって。
山田氏:
竹沢さんと僕とすごく似てるなって思ったのは、結局、「自分のフィルターを通すこと以上に重要なことはない」と思っているところかなと思います。
まず第一に、「誰の何を解決するのか」ということがビジネスの基本だと思うんですよね。その時に一番リアルなのは、自分が欲している空間や環境やものだと思うんです。世の中、山ほどものがあるのはなぜかって、みんな作りすぎている。でも自分が最高に欲しいものだとしたら、少なくとも自分と同じ課題を持っている人たちは買ってくれるわけです。逆にそのフィルター以外で作ったものって、仮説検証できない。これが誰のために作られたものかわからないから。自分が強烈に欲しいものであれば、年齢層とかターゲットとかどうでも良いと思うんです。
例えば、ネクタイが一番売れている場所ってダイソーなんです。年間200万本売れている。それが悪いということではなくて、ポリエステルが改良されてシルクに似た質感ができるようになっていて、それが売れている。なので、ファストファッションのレベルが高いからこそ、僕たちは絶対に譲れない領域を目指していかないと戦えない。自分が最高に欲しいかってものを作らないと厳しいんじゃないかと思います。

土屋氏:
ちなみにファクトリエでの商品開発はすべて山田さんが企画をされるのですか?
山田氏:
僕が企画するものもありますが、企画チームに任せるときは、その担当者が本当に欲しいのかどうかを基準にします。トレンドとか、売れているらしいとか、そういうことは却下します。
先日発表した白いデニム『児島のずっときれいなコットンパンツ』は、墨汁でもどんなものでも弾くっていう素材を使っています。実は担当者自身が、夏に白パンを履きたいけど、ワインやラーメンをこぼして履けなくなるっていう課題を解決したいという想いがあって作ったんですよね。そして、それを実現できる技術を探した。そういう強烈な想いが大事だと、商品開発会議の時にはいつも言ってますね。
大前氏:
自分的にメッセージを伝える努力はしていますが、第三者に補ってもらうことも大切にしています。一つは提供したお客さまや世の中、パブリシティも含めて、そういうところに代弁してもらうっていうのはありますね。
あとは本音を言う。2000名くらいの組織になると、どうしても洋服を着た議論になりがちです。例えば、1年目でも活躍できる場や、職位を語らない関係性、職位ではなく名前で呼ぶとかそう言うことはやっていますね。あとはメッセージをどう伝えるかについては、信頼している人、向いている人に任せるようにしています。

常識を疑う。体に聞く。楽しくないか聞く。
土屋:
最後のテーマは、「やらない決断」について。やりたいことがある一方で、やらないことの判断もあったと思います。
山田氏:
ただのアパレルにならないってことですね。みんな常識に引っ張られてしまうので。アパレル業界って消化率というのがあって、だいたい50~60%くらい。半分くらいは捨てる前提なんですよね。去年アメリカで未使用で捨てられた洋服が5兆円です。これがアパレルの当たり前。
僕たちはその全く逆です。僕たちの原価率はおよそ50%、最近は60~70%に上がっているものもあって、それ故できないことだらけです。ショッピングセンターには出せないし、セールやってたら原価割っちゃうし、卸もできない。なので、できないことはたくさんありますし、やらないことは最初からやりません。その分、やれることは全部やります。去年の秋に、横浜のお店を閉めたんですね。自分たちのコンセプトにあってやりたいんだけれども、うまくいくかどうかの決断は悩ましいですね。ここは葛藤しかありません。

竹沢氏:
RYOZANPARKに色々な場所からシェアオフィス、シェアハウスを一緒にしないかというお声がけをいただくんですが、基本お断りしています。やっぱり自分が目の届く範囲で、会えば「元気?」と言えるような距離感がない場合、基本的には作らない。話にはのらないようにしています。この巣鴨で100年くらい住まわせてもらっていて、次の100年のロングビジョンを考えたときには、遠くに投資するのはどうかなと思っています。
あとは全然参考にならないかもしれないですが、頭で考えるよりも、体に聞くようにしていて。ジムで筋トレをして反射神経を鍛えるというのをやるんですね。頭で考えるよりも体がどうリアクションしたかというのを信じる方です。自分の体が欲しているの?欲していないの?その感覚を持つためには、野生に戻って山を駆け巡ったり、海に潜ったりしたいけれども、なかなかその時間も取れないので、シェアハウス内にあるジムで筋トレしています。

大前氏:
体に聞くっていうのはわかりますね。僕は全く鍛えていないですし、ジムも嫌ですけど(笑)。ギターのウォーミングアップでメカニカルに指を動かすとか、すごくいい感じで、その直後に降りてくるみたいなのはありますね。体との連動ってあると思いますね。
金融の場合、お金儲けのビジネスをやるときには、金融庁にこういう商売をしたいのだけどやっても良いかという申請をして、クリアしなければならないんですね。年間20~30本くらい、具体的な施策を生み出しています。ジリジリと我々の「遊び場」の境界線、こっちまで行ったらアウトだよ、っていうそのラインを確認しながら領域を広げていく。思い描くこと全部ですね。

ただそれを実行するというレベルの話では、もちろんやらないこともあります。やらない決断をするときは、リターンというよりも調整コストを大事にしていて。それは儲かる儲からないではなくて、内部の職員やお客さまなど、そのプロジェクトを成り立たせるために、調整していかなければならない諸々があまりに大きすぎる場合。「それって楽しい?」って聞くんです。楽しくなさそうだなと思ったらやめる。
実際に過去にあったのですが、頭ではいいことだと思っていても、参加メンバーで共有感が作れないと感じた時は直ちにやめる決断をしました。そこまでかかった費用を損切りしてでも、もうこれは本当にごめんなさいと。みんな辛そうだねっていうときは、やっていてもしょうがないかって。
寂しさも嬉しさも本音と向き合う。そしてシェアをする。
質疑応答では、参加者より「社員との付き合いかたで一番大事にしていることはなにか?」という質問が出ました。

山田氏:
反省していることが一つあって。社員とは三ヶ月に一度、個人面談をしているんですが、一ヶ月後くらいの夜、面談したばかりなのに個人から僕宛にメールがくると、だいたいそれは「退職したい」っていう連絡なんです。それを見ると僕はすごく寂しくなる。
寂しいのは二つあって、辞めるって言われると、自分を否定されたような気持ちになってしまう、ということ。もう一つは、先月個人面談して本音で話したつもりだったのに、どうして先月の個人面談で相談してくれなかったんだろうっていう寂しさ。そういうときに究極のところ、僕自身が本音を言えてなかったんじゃないかと思うんです。それ故に壁があったんじゃないかって。

辞める人は起業するって人も多かったので、僕は起業を応援しようっていつも言うのですが、僕が本当に言うべきは、「応援してる。ただ僕は寂しい。辞めることも、相談してもらえなかったことも寂しい。そして壁を作ってしまっていたことも反省している。だから、これからもし何かあればいつでも言ってほしい。」と。それを僕は全員の前で言えなかった。でもそれを僕は言うべきだった。
どちらかと言うと未来志向なんで、未来はこうなんだとだからやるんだって考えがちで、こういう目の前の辛いところを見ないようにしていましたが、こういうところから目を逸らしてはいけないのだなと最近、思っています。
竹沢氏:
うまい肉をゲットしたら、みんなでシェアした方が美味しい!と思うんです。バーベキューは一人で食べるより、みんなで食べた方がおいしいでしょう。嬉しいこと、美味しいものは、みんなでシェアすればその価値は2、3倍に膨れる気がするし、逆に悲しいこと辛いことは、10分の1、100分の1で済む気がする。
そんな風にこれからは物だけじゃなくて、感情まで含めた、有形無形のものをシェアしていくという姿勢を大切にしています。それを社員だけでなく地域にも開いていく場所にして行きたいです。
笑顔の大前氏「参加者の間から具体的な動きを期待」
およそ2時間にわたったトークセッションは盛況のうちに終了。その後、終了時間いっぱいまで登壇者と参加者、参加者同士が交流を深めました。

大前氏は「想定以上のお客さまにお集まりいただき、本当に感謝しています。またこのイベントをきっかけに横のつながりに発展していくことを期待しています。参加者の皆さまの中から、それぞれの描く経済圏を実現するサービスや商品が1つでも2つでも生まれてほしいです。そうした積み上げが地域を元気にしていくのだと思います」と語りました。